愛すべきうしなわれたものたちへ
葬 列
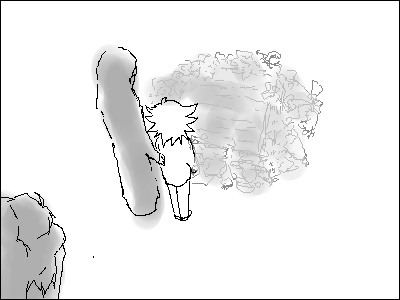
|
―――誰かが遠くで泣いている。 さざ波のように、すすり泣く声があちらこちらから漏れ聞こえてくる。まるで海の真ん中にいるみたいだとおれは思う。海の真ん中のなにもない小島にひとりっきりで取り残されたみたいだ。 おれは目を閉じる。誰かがおれを呼んでいるような気がするけれど、たぶんそれはおれの気のせいだ。だっておれを呼ぶひとはもういない。誰も。そう、もう誰もいないのだから。 パチパチと何かがはぜる音が聞こえる。何かが―――おれの大切ななにかが。燃えてしまう。消えてしまう。おれを置いてなくなってしまう。置いていかないでと叫んだらその願いは叶えられただろうか?おれの指先はこうして空を掴むことなく・・・・・・、 誰かがおれの名を呼んでいる。目を開けると、真っ黒な服の女が赤い瞳でおれを呼んでいた。さあ行きましょう遊星くん。お別れをしなくちゃ。女は屈みこみ、おれの手をとった。ちいさな手。幼くやわい子どもの手だった。 そう、おれはまだほんのちいさな子どもだったのだ。何もかもを持っていて、そして突然、ほんとうに突然にその何もかもをうしなってしまった幼く哀れで悲劇的で、そして幸福な子どもだった。おれはうしなったことすら知らずに不思議そうに首をかしげて、高々と積み上げられた花束を見つめていた。さあお花を置いて、と女が云う。おれはその花を手放したくなくて首を振る。女は困った顔でおれの手を握った。おれは首を振って、その手を拒んだ。可愛くてきれいな2本の花。このピンクのお花はおかあさんに、この白いお花はおとうさんにあげたいからとぎゅっと握り締めていた。たどたどしくそう告げると、女は耐えかねたような顔をしておれを抱きしめた。あのね遊星くん、遊星くんのおとうさんとおかあさんはね・・・・・・ 女の黒い服は喪服だった。おれを抱きしめた腕は震えていた。寄せられた頬は濡れていた。そんなことばかりしっかりと覚えているのに、おれは棺の中に眠る父さんと母さんの顔も思い出せない。 いろんなひとが泣いていた。あんなにたくさんの泣き顔を見たのはきっとおれの生涯であれっきりだろう。すすり泣きと絶望と悲嘆のなかでおれは立ち竦んでいた。足元からひたひたと海が押し寄せてくる。真っ黒な、夜の海。嘆きの海だ。それはすこしずつ、すこしずつおれを引き寄せてゆく。いつかおれは溺れてしまうかもしれない。首までつかり、そして頭のてっぺんまで海に掴まってしまったらおれも父さんたちとおなじところにいけるんだろうか?甘く強い花の芳香がおれを引き寄せる。水の音、花のにおい、泣き声、遊星、誰かがおれを呼んでいる、父さん、母さん、いたる方向から音は聞こえてきておれはどちらに行けばいいのかわからなかった。 ・・・遊星。だれかがおれの名を呼んでいる。―――遊星!! ハッと目を覚ますと、そこはいつもの部屋だった。真っ暗な、サテライトでのおれのねぐら。暗闇のなかで紫電の瞳がおれをじっと見つめていた。心配そうに。 「・・・うなされていたぞ遊星、大丈夫か?」 ああ大丈夫、そう答えようとして初めて自分の頬が濡れていることに気がついた。黙りこくるおれにそっと伸ばされた腕は白を纏っている。強く引き寄せられた腕の中で、おれは目を閉じた。花の匂いはもうしなかった。波音ももう聞こえず、代わりに油とほこりと雨のにおいがしていた。 ・・・ただ遠くから聞こえる誰かのすすり泣く声。 もしかしたら、あれはいつかの幼いおれの泣き声なのかもしれなかった。 |
不動さんの過去を妄想すると泣けてくるわ・・・
ほんとうは不動さんの両親が亡くなったとき、もっと幼いはずなんですが
そのあたりは妄想乙ということで勘弁してください・・・。
2008.11.20